
「0800-500-0178」という見慣れない番号から突然の着信。
しかも自動音声で「電気料金の調査にご協力ください」と言われたら、不安になって当然です。
「これって本物の電力会社?」「応答したら何か問題あるの?」「無視していいの?」と戸惑ってしまう人も多いはず。
最近では、こうした自動音声を使った“電力アンケート”風の営業電話が急増しており、迷惑電話や詐欺まがいの手口としてネット上でも多くの口コミが寄せられています。
とくに、回答を促されるボタン操作や、後日別番号からの営業電話といった流れには注意が必要です。
この記事では、「0800-500-0178」の発信元や通話内容の傾向、ネット上の評判、そしてもし着信があった場合の具体的な対処法や相談窓口まで、実体験をもとにわかりやすく解説しています。
この記事を読めば、この番号が本当に危険なのかどうか判断でき、不安なく行動できるようになります。
不審な着信に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
0800-500-0178 ― 発信元と正体
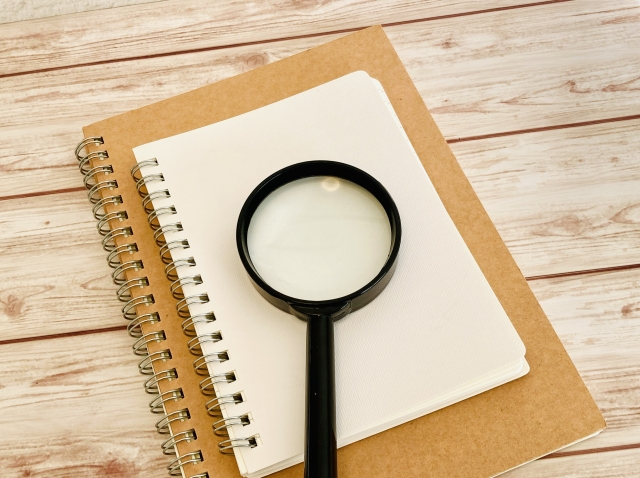
番号種別
この電話番号はKDDIが提供するフリーダイヤル(0800)番号に分類されます。
0800から始まる番号は、通話料を着信側が負担する仕組みで、企業や団体による問い合わせ受付や営業活動に広く使われています。
中には正規の企業もありますが、最近ではこのような番号を悪用した迷惑電話や詐欺まがいの電話も増加しています。
名乗り方
この番号からの着信は、ユーザーの報告によると、自動音声ガイダンスが流れる形式が主流で、「電気料金調査センター」「エネルギー調査窓口」など、いかにも公的・中立的に聞こえる名称を名乗るパターンが多く見られます。
通話内容としては、「電気料金について数問のアンケートにご協力ください」と案内された後、いくつかの質問に答えるよう促され、その後、営業担当者につながる、もしくは別番号から再度営業電話がかかってくるといった流れが報告されています。
実際のところ、このような発信に対して、正式な電力会社や登録された小売電気事業者からの公式な発信であると裏付ける情報は確認されておらず、信用に値しないと判断するのが妥当です。
jpnumberなどの電話番号情報共有サイトにおいては、この番号の事業者名として「ニセ電力会社」と明記され、業種も「自動音声詐欺電話」と分類されています。
これにより、正規の企業ではなく、情報収集や契約誘導などを目的とした不審な発信元である可能性が極めて高いことがうかがえます。
ネット上の評判・口コミ

| サイト | 迷惑電話判定 | 口コミ件数・内容の傾向 |
|---|---|---|
| 電話帳ナビ | 迷惑電話度 94 % | 「蓄電池・電力切替営業」「自動音声アンケートは犯罪に利用される事があります」など、500件を超える口コミが寄せられています。多くのユーザーが「留守番電話にも残された」「昼夜問わずかかってくる」といった被害を共有しており、単なる営業電話ではなく不快な体験として認識されています。 |
| jpnumber | 1,300件超の書き込み | 「電気料金に関する簡単なアンケート」として始まる通話が多く、実際には最終的に営業担当につながる、あるいは後日再勧誘されるといった報告が続出。特に広島・岡山エリアでの報告が目立つことから、特定の名簿リストをもとにかけている可能性も指摘されています。 |
| X(旧Twitter) | 「#迷惑電話」「0800は出ないで」など注意喚起ツイートが散発 | 「いきなり自動音声」「ボタンを押してしまったけど大丈夫?」という投稿もあり、利用者の不安が広がっています。さらに、複数のユーザーがこの番号に共通する着信パターンを指摘し、同様の手口が繰り返されているとされています。 |
| Yahoo!知恵袋 | 「3秒で切ったが今後大丈夫か」「折り返さない方が良い」等の相談多数 | 回答の大半は「詐欺の可能性があるため無視すべき」「情報提供は一切避けるべき」といった注意喚起が目立ち、過去の同様のケースに照らしても警戒すべき番号とみなされています。口コミには、実際に個人情報を聞かれた事例もあり、安易な応答がトラブルの火種になることが懸念されています。 |
この番号は実在企業のカスタマーサポートや公式窓口としての実績はなく、多くのユーザーから“自動音声+電力アンケート”という形での不審な接触が報告されています。
着信の内容や手法、繰り返される報告内容から判断して、迷惑/詐欺系コールとしての要素が非常に強く、十分な警戒が必要です。
なぜ迷惑電話扱いされる?

自動音声で一方的に選択肢を押させる
「使用量が○円以上なら…」「当てはまる番号を押してください」などと案内され、電話の受け手に対して選択を強要するような形式が多く報告されています。
これにより、受信者の反応や操作内容を記録し、その電話番号が実際に使用されているかどうか(=生きた番号かどうか)を確認する手口と一致します。
また、一度ボタンを押すと、それをトリガーとして別の営業電話がかかってくるケースや、他の業者に転送される事例も確認されています。
本物の電力会社は0800でアンケートをしない
本来、電力会社などのインフラ企業が自動音声を用いて個人宅にアンケートを依頼することは極めてまれです。
特にフリーダイヤルを使用し、かつ個人情報に関わる内容を尋ねるような形式は、ほとんど見られません。
総務省や消費者庁の公式情報にもある通り、「正規の事業者が自動音声で契約や生活情報を聞き出すことは基本的にない」と明確に注意喚起されています。
地域無差別に発信
この番号に関する口コミは、全国各地から寄せられており、北海道から九州まで広範囲で確認されています。
これは、地域を問わず一斉に発信されていることを示しており、名簿リストを用いた大量発信や、自動発信システムの利用が疑われる根拠の一つです。
実際、似たような電話が連日何度もかかってくるという声もあり、電話番号の管理者が悪質なコールセンターや営業代行業者である可能性が高いと考えられます。
着信してしまったら? ― 3つの安全対処法

① 応答しない/途中で切る
この番号に限らず、見知らぬ番号や自動音声ガイダンスによる電話には応答しないことが最善です。
通話料は基本的に無料でも、電話を最後まで聞いたり操作したりすることで、電話会社や悪質な業者に「この番号は使用されている」と認識されてしまい、その後、再度ターゲットにされやすくなります。
特に途中でボタン操作などを行うと、積極的なリストに追加されるリスクがあるため、すぐに通話を切るのが安全です。
② 端末側でブロック
着信履歴から該当番号の右横にあるⓘをタップし、「この発信者を着信拒否」に設定することで、同じ番号からの再着信を防ぐことができます
Android(Pixel例): 通話アプリで履歴を開き、対象の番号を長押しして「ブロック」または「迷惑電話に登録」を選びます。
加えて、NTT東日本や主要携帯キャリアが提供している迷惑電話ブロックアプリ(例:あんしんセキュリティ、迷惑電話ストップサービスなど)を活用することで、より広範囲な迷惑番号を自動検知してくれます。
特に高齢者やスマホ操作に不慣れな方には、家族による設定支援もおすすめです。
③ 個人情報は絶対に入力・口頭回答しない
自動音声が誘導する質問に対して、たとえ選択肢を押すだけでも個人情報が間接的に収集される恐れがあります。
「はい」「いいえ」などの回答はもちろん、「使用している電力会社」「電気代の平均額」「在宅時間帯」「家族構成」など、生活に関わる情報が意図せず渡ってしまうリスクがあります。
こうした情報は、別の業者や詐欺グループに転売され、さらなる勧誘や架空請求などの被害につながるおそれもあります。絶対に答えないように注意しましょう。
もしトラブルになったら相談できる窓口

| 窓口 | 連絡先・受付時間 | 相談できる内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 電話 188(いやや!) ※最寄りの消費生活センターに自動転送 | しつこい勧誘・個人情報を渡してしまった後の対応 |
| 警察総合相談窓口 | #9110(全国共通・平日対応) | 詐欺被害の恐れ、脅迫めいた内容、振り込み指示など |
| 匿名通報ダイヤル(特殊詐欺) | 0120-924-839(平日 9-17時) | 振り込め詐欺グループなど犯罪情報提供 |
| 契約関連の相談(電力切替・クーリングオフ) | 消費者センター or 監督官庁(経済産業省 資源エネルギー庁) | 勧誘で契約してしまった場合の解約手続き |
まとめ ― 覚えておくポイント
-
正式な電力会社・官公庁が0800-500-0178を業務連絡に使う事実は確認されていません。どれだけそれらしい名称を名乗っていても、信頼できる情報源から確認が取れない以上、安易に信用してはいけません。特に「電気料金調査センター」や「エネルギー相談窓口」などの曖昧な名称には注意が必要です。
-
自動音声で家庭の電気料金を聞き出す手口は、名簿づくりや詐欺営業で典型的な方法です。こうした情報は、その後の営業電話や詐欺行為につながる「予備情報」として悪用されるケースも多く、安易な回答が個人の不利益につながる恐れがあります。
-
着信したら「出ない・押さない・折り返さない」が鉄則です。特にボタン操作は「この番号は反応がある」と判定され、他の業者への転売対象になる可能性もあります。少しでも不審に思ったら、即切断・着信拒否を心がけてください。
-
被害や不安があれば 188(消費者生活センター)か #9110(警察相談)へ迷わず相談を。被害が未然に防げるだけでなく、同様の通報が集まることで、当局の対策や調査が進むきっかけになります。ひとりで抱えず、まずは相談することが大切です。
-
スマホの着信拒否機能とキャリア提供の迷惑電話ブロックサービスを併用することで、再着信リスクを大幅に減らせます。特に「番号自動識別機能」や「迷惑度判定」がついたアプリを活用すれば、知らない番号からの着信そのものを未然に防げるケースも多くあります。高齢の家族がいる場合は、あらかじめこれらの設定をしておくと安心です。
「無料だから安全」という思い込みは禁物です。フリーダイヤル番号であっても、その背後にある意図や目的はまちまちであり、中には情報搾取や詐欺まがいの悪質なケースも含まれています。
少しでも「おかしい」と感じたら、冷静に対応し、信頼できる第三者に相談することをためらわないようにしましょう。
自分自身や家族を守るためにも、日頃からこうした危機管理意識を持っておくことが何より重要です。